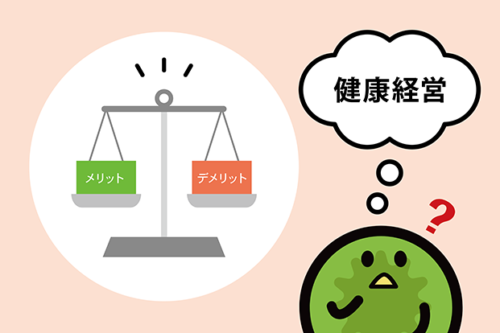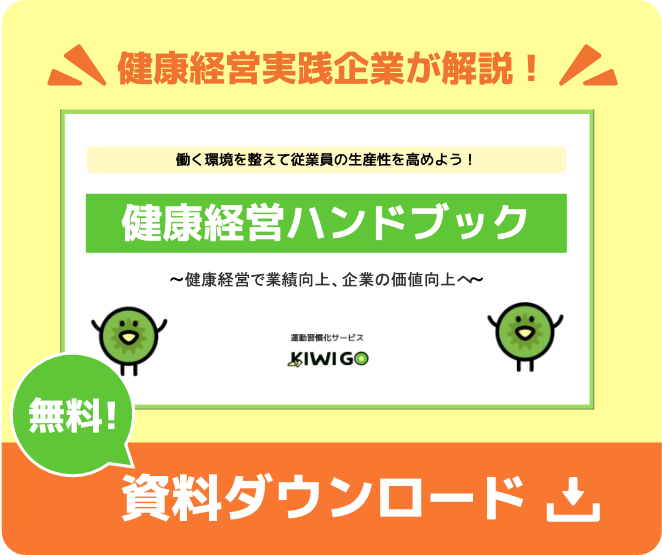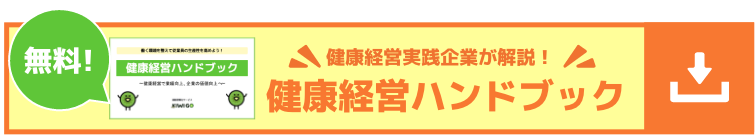近年、働き方の変化に伴い社内で運動に取り組む企業が増えています。
しかし企業として、どのように従業員の健康管理をすればよいか分からず悩む企業は多いでしょう。
とくに社内となるとできることが限られるため、多くの従業員が参加できる取り組みを考えるのは難しいです。
そこでこの記事では、社内で運動に取り組む効果やメリットに加え、具体的な方法や事例も紹介します。企業主体の取り組みで従業員の健康を促進させましょう。
運動不足を解消し、従業員の健康を促進するKIWI GOの活用事例集はこちら
目次
働き方の変化と健康課題

日本では少子高齢化による労働人口低下への対応策として、テレワークが推進されています。
国土交通省の調査では令和3年度、勤務先に「テレワーク制度が導入されている」と回答した人は40.0%でした。現在、企業と雇用契約を結んで働いている雇用型就労者のうち、テレワークを行っている人の割合は全国で27.0%と過去最高値です。特に首都圏では42.1%と高い割合となっています。
テレワーカーが増加するなか、株式会社アジャイルウェアが行った調査では75.5%の人が「1日の歩数が減った」「外へ出ない日がある」と運動不足を実感しています。
参考:株式会社アジャイルウェア リモートワークと運動習慣のアンケート
運動不足になると筋力が低下し姿勢が悪くなります。姿勢の悪さは頭痛や肩こりの原因になり、従業員のパフォーマンス低下につながる可能性も高いです。
テレワークでは運動不足以外に下記の課題が生じています。
- 長時間労働が起こりやすい
- コミュニケーションが取りづらい
テレワーク環境では、企業側が従業員の不調に気づきにくいです。従業員の健康のため、心身ともに企業として対策を行うことは重要です。
社内で運動に取り組むメリット

社内で運動に取り組むことで、企業が得られるメリットを3つ紹介します。
従業員の運動習慣を促せる
スポーツ庁の調査によると、運動不足を実感しているにも関わらず運動頻度が週に1日以下の人は約4割です。特に働き盛りである20代~50代では、運動頻度の少ない人の割合が上がります。運動ができない理由としては、「仕事や家事が忙しいから(42.6%)」「面倒くさいから(39.2%)」が多いです。
参考:スポーツ庁 令和3年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」
この調査から、個人で運動をする時間を見つけて実施することのハードルは高いと分かります。
個人で運動をするのが難しい状況では、1日の大半を過ごす会社で運動を取り入れることが重要です。
勤務時間内に運動を促し、運動の習慣化を目指しましょう。
従業員のパフォーマンスが上がる
筑波大学の研究では、ヨガや太極拳のような超低強度運動を10分間行うことで、直後に記憶力が向上することが明らかになりました。記憶力が上がることで、従業員の作業効率の向上が期待できます。
さらに週に数回ウォーキングを行うことは、脳機能に好影響を及ぼすと分かっています。
アンダース・ハンセン著の『一流の頭脳』によると、運動をすることで集中力や記憶力が高まり、情報を効率的に処理できるようになります。
従業員ひとりひとりのパフォーマンスが上がれば、企業価値のさらなる向上も見込めます。
参考:『一流の頭脳』(2018年)著者: アンダース・ハンセン/訳者: 御船由美子
社内のコミュニケーションを促進できる
運動に関連するイベントを開催することで、従業員同士のコミュニケーションの機会が増えます。
テレワーク環境でもコミュニケーションを取る機会が増えれば、孤独感を感じにくくなり従業員のストレス軽減にもつながります。
社内で運動に取り組む具体的な方法

ここでは実際に社内で運動に取り組む際の具体的な方法を紹介します。
ウォーキング
ウォーキングは体力の有無や年齢問わず気軽に始められる運動のひとつです。
厚生労働省も日常の歩数の増加を目標にしています。20歳~64歳における1日当たりの歩数の現状値は、男女ともに目標値に1000歩以上足りていません。
|
現状値 |
目標値 |
|
|
男性 |
7864歩 |
9000歩 |
|
女性 |
6685歩 |
8500歩 |
日常生活でウォーキングを取り入れるには、階段を使う、通勤時にひと駅分歩くなどちょっとした習慣の切り替えが大切です。歩くことを普段から意識してもらうため、チャットツールや社内報などでウォーキングの重要性を伝えましょう。
また社内ウォーキングイベントを開催する、歩数に応じてインセンティブを与えるなど、従業員が楽しく取り組めるよう工夫することも大切です。
スタンディングミーティング
打合せ時にスタンディングテーブルの利用を推奨することも、運動習慣を促す方法のひとつです。
日本人は1日で座っている時間が世界で一番長いと言われており、死亡リスクの高い状態にあると言えます。
参考:東洋経済オンライン 死亡リスク4割増「座りすぎ日本人」の絶大リスク
長時間の座りっぱなしを防ぐことで筋力が強化され、血行促進効果も得られます。こまめに立ち上がるよう呼びかけましょう。仕事が忙しい従業員にも、スタンディングテーブルで運動習慣を促してください。
社内運動会
社内運動会を開催することは運動不足解消だけでなく、社内のコミュニケーション促進にも役立ちます。
従業員が協力してひとつのことに取り組むことで、コミュニケーションの機会が生まれます。従業員同士の団結力が高まれば、業務の円滑化につながります。
しかし社内運動会の開催には時間と手間がかかります。運動会の実施が難しい場合、設備がなくても開催できるウォーキングイベントがおすすめです。
ヨガ・ストレッチ
ヨガやストレッチは、体力に自信がない人や女性も参加しやすい運動のひとつです。
ストレッチは業務の隙間時間で気軽に取り入れることが可能です。部署内で一緒に取り組めば、コミュニケーションの活性化にも役立ちます。そして深い呼吸とともに体と心を整えるヨガは、定期的に行うことで心身ともにリフレッシュできます。メンタルケアの一環として、ヨガの実践もおすすめです。
ヨガやストレッチの講座を行う場合、場所の確保やインストラクターの派遣が必要です。事前にしっかりと準備を行いましょう。
運動は楽しく継続してもらうことが大切

運動でもっとも重要なのは、従業員が楽しく続けられるかどうかです。
どのような運動なら取り組めるかアンケートを取り、1人でも多くの従業員が運動できる環境を作りましょう。部署で協力する、チーム対抗のイベントを開催するなど、楽しみながら社内全体で気軽に運動する雰囲気を作ることも重要です。
また運動習慣のない従業員にも参加してもらえるよう、ゲーム感覚で運動できるアプリを活用しましょう。軽い運動であっても、楽しく継続できることがもっとも大切です。運動しない従業員を責めるのではなく、全員が楽しく取り組めるよう工夫しましょう。
社内で運動を取り入れた企業の事例

ここでは企業の事例をもとに、社内で運動を取り入れたことでどのような効果があったか紹介します。
ネッツトヨタ山陽株式会社

出典:ネッツトヨタ山陽株式会社
ネッツトヨタ山陽株式会社では、風通しのよい「働きやすい職場づくり」をテーマに、トップ主導で様々な健康経営の取り組みを行っています。
おもな取り組みは以下の通りです。
- 電子万歩計を社員に支給
- 歩数を集計して毎月発表
- ウォーキングコンテストを実施
- 全社員でのラジオ体操
- 社員食堂でヘルシーメニューを提供
- 外部講師によるセミナー
これらの取り組みが評価され、健康づくりに積極的な企業として県から表彰されました。
社内外に取り組みが発信されたことで、ネッツトヨタ山陽株式会社では健康作りをきっかけとしたコミュニケーションが増加しました。
また面接時に健康づくりについて興味を持つ応募者も増え、採用にも良い影響が出ています。
SCSK株式会社

出典:SCSK株式会社
SCSK株式会社では、従業員の健康が経営上の最重要事項であるととらえ、健康づくりに積極的に取り組んでいます。
数ある取り組みのなかで特徴的なのは、健康に良い行動習慣をポイント化し一定基準を満たせばインセンティブを支給する「健康わくわくマイレージ」です。
インセンティブを目標にして健康わくわくマイレージに取り組む従業員は多く、導入後のウォーキング実施率は53%に増加しました。
またSCSK株式会社では従業員と家族を対象としたウォーキングイベントを実施するなど、健康に関するイベントも行っています。平日に歩行などの運動習慣がある人は、運動習慣のない人と比べ仕事の生産性が高いと回答している割合が高いです。
また「健康状態の良さが高いパフォーマンスにつながっている」と感じた従業員の割合も92%に増えたため、取り組みにより健康意識が高まったと言えます。
ウイングアーク1st株式会社

ウイングアーク1st株式会社は原則在宅勤務であるため、運動不足やコミュニケーション不足を改善する様々な取り組みに力を入れています。アプリを活用した全社ウォーキング大会では、従業員の歩数を距離換算し地球1周を目指す取り組みが行われました。全従業員で運動に取り組む意識付けを行うことで、参加率は80%を超えました。
またイベントの開催をきっかけに「これからもウォーキングを継続したい」という声も出ており、従業員の運動促進にも成功しています。
さらにお昼休みにはPCのカメラを使いラジオ体操やストレッチを行い、イベント以外でも体を動かすきっかけを提供しています。ラジオ体操やストレッチを通じて生まれる会話は、気分転換にもつながると従業員から好評です。
参考:スポーツ庁 「スポーツエールカンパニー2021」認定企業の取組事例
公益財団法人明治安田厚生事業団

公益財団法人明治安田厚生事業団では職場を活動的にするため様々な取り組みを行っています。おもな取り組みは以下の通りです。
- スローエアロビクス
- ランチタイムウォーク
- ウォーキングアプリを使った歩数チェック
- スタンディングミーティング
- 座りっぱなしブレイク
座りっぱなしブレイクは、座る時間が長くなる会議中に声を掛け合い、エクササイズを行う取り組みです。サイコロを振ってエクササイズを決め、全員で取り組みます。部下も上司も一緒にリフレッシュできる取り組みであるため、コミュニケーションの増加につながっています。
スタンディングミーティングは、体の負担を軽減できるだけでなく意見の活発化にも役立っています。
業務中にできる取り組みを多数導入することで、公益財団法人明治安田厚生事業団はスポーツ庁からスポーツエールカンパニーとして認定されています。
参考:スポーツ庁 「スポーツエールカンパニー2021」認定企業の取組事例
まとめ:運動への取り組みは会社全体の向上につながる

社内で運動に取り組むことで従業員の健康が促進されるだけでなく、コミュニケーションの機会も増加します。
従業員が健康でいきいきと仕事に取り組むことができれば企業全体も活発化し、企業価値向上にも期待できます。
従業員の運動習慣を促すきっかけ作りとしておすすめなのが、企業向け福利厚生アプリ「KIWI GO」です。
「KIWI GO」では歩数に応じたポイントが貯まり、貯まったポイントを好きなごほうびと交換できます。ゲーム感覚で始めることができるので、普段運動習慣のない人でも歩くことを意識づける良いきっかけになります。チームを作ってイベントを開催することもできるので、従業員同士のコミュニケーションを促すのにもおすすめです。
従業員の運動習慣やコミュニケーションに課題を感じている企業様は、ぜひ導入を検討してみてください。

従業員の不調があると業務が円滑に進まなくなり、企業の業績に悪影響が出る可能性があります。
また社会としても従業員が健康に働ける環境が重視されており、健康に関するイベントや企画を実施している企業は多いです。
しかしどのような企画であれば従業員に参加してもらえるのか、悩んでいる企業もあるでしょう。この記事では、すでに企業が行っている健康イベント企画の事例を紹介します。
実際にイベントを開催するためのステップも詳しく解説するので、従業員が楽しく参加できるイベントを企画するために最後までご覧ください。

健康イベントで健康増進を行うメリット

健康イベントへの投資効果を実感するには時間がかかりますが、従業員の健康をサポートすることで長期的なメリットが得られます。
楽しく健康イベントに参加することで従業員自身が健康を維持できるようになり、安心して前向きに働けるようになるでしょう。また病気による休みが減り、業務が円滑に回るようになります。
そして従業員間のコミュニケーションが生まれることで業務におけるやり取りがスムーズになり、組織全体としての連帯感も強化されます。
健康への取り組みを行えば、企業のイメージ向上にも効果的です。採用活動における優秀な人材獲得にもつながるため、健康イベントに力を入れるメリットは大きいといえます。
健康増進イベントの企画例6選

以下では、健康増進イベントとして定番の企画を6つ紹介します。アイデアが思いつかずお悩みの人は、ぜひ参考にしてください。
ウォーキング
ウォーキングは年齢を問わず手軽にできる運動の一つです。楽しく継続してもらえるよう、イベントとして企画しましょう。
東京都健康長寿医療センター研究所の調査では、1週間に40分以上歩くだけで認知機能が改善するとわかっています。従業員の仕事の質を向上させるため、ウォーキングは非常に効果的です。
実際に兵庫県川辺郡猪名川町では、市民の健康増進イベントとして100万歩チャレンジを開催しました。100日間で100万歩達成、と明確な目標を作ることで、多くの方が楽しく参加できるイベントとなりました。新型コロナウイルスなどの事情を考慮し、座った状態でもできる筋力トレーニングやストレッチのコースを用意しているのもポイントです。
出典:兵庫県川辺郡猪名川町 2022いながわ100万歩チャレンジ!
ゴミ拾い
ゴミ拾い活動も健康増進に役立つイベントの一つです。ゴミ拾いの本来の目的は暮らしやすい街づくりであり、地域社会に貢献する施策としても有効です。特に近年では環境や健康、人権を守るための世界的な目標、「SDGs」が注目されています。
ゴミ拾いの活動は、SDGsの11番目の目標「住み続けられるまちづくりを」に該当するといえるため、社会貢献として重要な位置づけの企画です。
出典:外務省 JAPAN SDGs Action Platform
1度限りの企画で終わらないよう、定期的に職場周辺のゴミ拾いイベントを開催しましょう。ゴミ拾いとスポーツをかけ合わせ、競技として取り組む「スポGOMI」というイベントも存在します。
スポGOMIではチームで集めたゴミの量を競うため、コミュニケーションのきっかけにもなります。従業員が楽しめるルールを作り、ゴミ拾いイベントを充実させましょう。
出典: 一般社団法人ソーシャルスポーツイニシアチブ スポGOMI
健康測定
企業で定期的に行う健康診断に加え、健康測定イベントを開催するのも有効です。定期的に健康測定イベントを行うことで、従業員の健康意識が高まります。健康機器を用いれば血液のさらさら度や骨密度を数値化でき、健康状態を詳しく簡単に把握できます。
またストレスや脳年齢なども測定可能であるため、健康に関する話題で従業員同士が盛り上がれるでしょう。健康機器のレンタルサポートをしている業者も存在するため、有効活用してください。
瞑想(マインドフルネス)
瞑想(マインドフルネス)とは、「今ここに集中する」ことで集中力や生産性を高める効果が期待できる手法です。慶應義塾大学病院の研究では、マインドフルネスで不安症状の改善効果がみられました。
出典:慶應義塾大学病院
アメリカはマインドフルネス先進国ともいわれており、AppleやGoogleをはじめとした名だたる企業がマインドフルネスに注目しています。日本国内においても、Sansan株式会社がマインドフルネス研修を実施した実績があります。
マインドフルネスではアクティブに体を動かす必要がないため、運動が苦手な従業員も取り組みやすいです。まずは勤務時間の合間にマインドフルネスを取り入れましょう。
ヨガ教室
ヨガは身体的なエクササイズとともに呼吸を整えることで、体と心の安定化を図る方法です。医学的にもヨガには肥満解消や血糖値の低下、ストレスに対する抵抗力アップといった効果が認められています。
松井産業株式会社では65歳以上の従業員を対象に、月3回のヨガ教室を社内で開催しており、従業員は自由に参加可能です。従業員だけでなく地域の高齢者も参加可能としているため、地域社会と連携しながら健康を実現できます。
出典:松井産業株式会社
睡眠改善プログラム
質の高い睡眠は、従業員の健康を高めるうえで非常に大切です。睡眠不足の状態では集中力や気力が落ちてしまい、怪我や事故のリスクが増大します。
厚生労働省によると、睡眠を1日6時間以上取ることで日中の眠気と疲労感が改善し、ストレスを感じにくくなります。また風邪にかかる確率やうつ状態になるリスクを低下させる効果もあるため、睡眠改善は安定した経営にもつながります。
出典:厚生労働省 こころの耳
株式会社フジクラでは、睡眠不足による生産性低下が示唆されたことから、睡眠セミナーを開催することで改善を図っています。セミナー形式で睡眠の重要性を伝えることで、習慣改善に役立ちます。
出典:株式会社フジクラ
取り組みのランキング化
健康イベントへの取り組み度をランキング化し、ゲーム感覚で健康増進を図るのも効果的です。
イベント参加で獲得したポイントでランキングを作り、上位に入賞すればAmazonギフト券が当たるなど魅力的な特典を付けましょう。ごほうびがあれば、より多くの従業員が楽しくイベントに参加できます。
またランキング上位に入らなくても参加賞などがもらえるよう工夫することで、従業員の参加率や満足度は高まります。個人別や地域別にランキングを可視化すれば、さらなるモチベーションアップにもつながるでしょう。
健康イベント企画の6ステップ
成功する健康イベントの企画には、準備段階が肝心です。
以下では、健康イベントを企画する際の6ステップを紹介します。従業員から高い満足度を得るためにも、ぜひ確認してください。
1.ターゲットを明確にする
まずはイベントのターゲットを明確にしましょう。ターゲットが決まると目的もおのずと決まり、従業員の興味をひけるイベントとなります。
例えば睡眠不足の従業員が多い場合、睡眠改善に関連する健康イベントが有効です。従業員の悩みやニーズを把握するため、メールや対面などでアンケートを取りヒヤリングしましょう。
2.イベント内容を決める
ターゲットの悩みやニーズを把握できたら、課題解決を目標にイベントの内容を決定しましょう。
従業員の参加率を上げるためは、景品を用意し参加のメリットを明確にしておくのがおすすめです。景品にかける大まかな予算も、この段階で決めておきましょう。そしてさらに健康イベントを充実させるには、イベントを企画する運営チーム側も楽しめるよう遊び要素を入れることも重要です。従業員側と運営側の双方が楽しく健康イベントに関与できれば、長期的にも成功する取り組みとなります。
3.イベントの開催日を決める
イベントの成功において、開催日も重要な要素です。
従業員のみ参加とする社内イベントであれば平日の勤務時間中がよいですが、従業員の家族も巻き込むのであれば休日が適切です。早めに開催日を告知し、スケジュールを調整してもらいましょう。遅くとも1か月前には開催日を決定しておくと安心です。
4.イベント会場や形式を決める
イベント当日を円滑に迎えるためには、イベント会場の確保も忘れてはいけません。健康測定など社内で実施する健康イベントであっても、会議室などの確保は必須です。
よい会場が見つからない場合、オンラインでのイベント開催もおすすめです。オンラインイベントの場合、Zoomなど会議ツールの動作確認をしておきましょう。
5.イベント開催の告知をする
イベント開催の告知は、従業員の参加率に直結します。参加してほしい従業員に効果的な訴求を意識し、告知文を作りましょう。
ターゲットが悩んでいる内容を提示し、イベント参加により得られるメリットを強調するのがコツです。なお、健康イベントは実施してすぐ効果が出るものではありません。
「高齢になっても健康的でいられる」といった長期的なメリットも告知文に含めるのがおすすめです。長い目で健康レベルを高める意識を持ってもらいましょう。
告知方法としては、社内の掲示板やメール・チャットツールが効率的です。多くの従業員の目を引くため、文章だけでなく画像やイラストも活用してください。
6.当日の様子を伝える
当日の様子を写真などで撮影しておき、イベント終了後に展開することでさらなるイベント参加率向上に役立ちます。今回参加できなかった人や興味がなかった人にも、イベントの魅力を知ってもらいましょう。
健康イベントは継続的に行うことが重要であるため、参加者にアンケートを記入してもらい、よかった点と悪かった点を整理してください。「次回は参加率を◯%にする」といった新たな目標を立てることで、より良い健康イベントとしてブラッシュアップできます。
まとめ:健康イベントは準備が9割!従業員が参加したくなる健康イベントを企画しよう
今回は、健康イベント開催までの流れや企画例について紹介しました。
健康イベントを成功させる鍵は、企画段階の綿密な準備です。何から始めたらいいかわからない人は、今回紹介したステップに沿って取り組みを進めていきましょう。
健康イベントは長期的に継続することが重要であり、従業員が率先して参加したくなるような工夫が必須です。
運動習慣化アプリKIWI GOには、楽しく運動を促す工夫が多数盛り込まれています。
イベント開催をサポートする機能、歩数をランキング化する機能もあるため、継続的に楽しいイベントを作るのに役立ちます。
従業員に運動習慣を身につけてもらうなら、ぜひKIWI GOを活用してみませんか。
KIWI GOに関する詳細は以下の概要資料にもまとめております。無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。