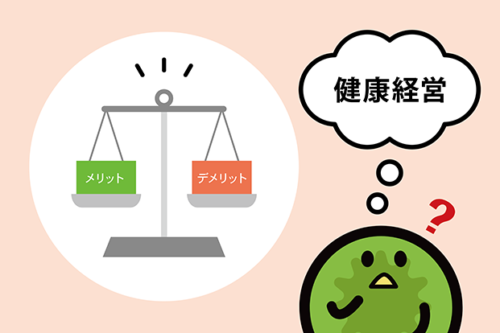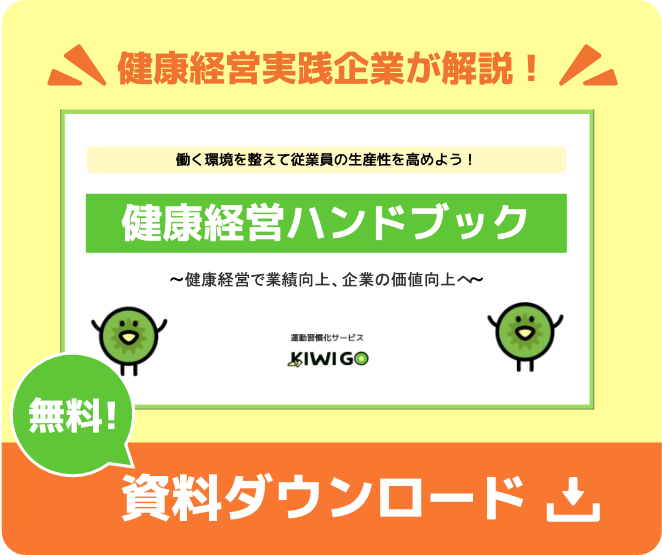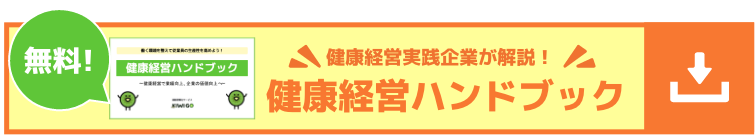「ウェルビーイング経営」という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。ウェルビーイング経営は、近年注目を集めている取り組みのひとつです。
しかし具体的にウェルビーイング経営で何をすれば良いのか、悩む担当者は少なくありません。
そこで本記事では、ウェルビーイング経営の概要や具体的な導入事例を解説します。またウェルビーイング経営のメリットや取り組みを導入する際のポイントも解説するため、ぜひ参考にしてください。
目次
ウェルビーイング経営とは?

まずは、ウェルビーイング経営の概要について解説します。
ウェルビーイング経営の考え方
ウェルビーイングとは、身体的・精神的・社会的に満たされた状態であることです。1964年にWHO(世界保健機関)が発表した言葉で、「世界保健機関憲章」に記載されています。
またウェルビーイング経営とは、ウェルビーイングを経営の中に取り入れ、従業員の健康をサポートする取り組みを指します。働きやすい環境作りを進めることで従業員満足度が向上し、エンゲージメントの向上効果が期待されます。
ウェルビーイングを構成する要素
ウェルビーイングは、以下の5つの要素で構成されています。
- キャリアウェルビーイング:仕事・子育てなどのキャリアに関する幸福度
- ソーシャルウェルビーイング:人間関係に関する幸福度
- ファイナンシャルウェルビーイング:経済的な幸福度
- フィジカルウェルビーイング:身体的・精神的な幸福度
- コミュニティウェルビーイング:地域社会に関する幸福度
上記は、アメリカの世論調査会社・ギャラップ社によって定義された要素です。世界的に有名な定義のひとつで、多くの企業で採用されています。ウェルビーイング経営を行う際は各要素を企業として満たせているか確認してください。
参考:ギャラップ社 The Five Essential Elements of Well-Being
あわせて読みたい:ウェルビーイングを構成する5つの要素とは?世界の動きと日本の現状
ウェルビーイング経営と健康経営の違い
ウェルビーイング経営と似た概念に「健康経営」があります。健康経営は、従業員の心身を健康にすることで企業の生産性を向上させるという経営戦略のひとつです。
あわせて読みたい:健康経営の進め方とは?組織体制の整え方や効果的に進める方法を紹介
健康経営とウェルビーイング経営の主な違いは「ゴール」にあります。健康経営は「従業員の心身の健康を維持増進させること」を目的としているのに対し、ウェルビーイング経営はその先の「心身共に満たされている状態・幸せを感じられる状態にすること」を目的としています。そのためウェルビーイング経営は、健康経営を内包する経営方針といえるでしょう。
また取り組みの導入方法にも違いがあり、健康経営はトップダウン型、ウェルビーイング経営ではボトムアップ型が採用されるケースが一般的です。
あわせて読みたい:ウェルビーイングと健康経営の違いとは?注目の理由や事例を紹介
ウェルビーイング経営のメリット

ここでは、ウェルビーイング経営を導入するメリットを3点紹介しま
従業員の人生の幸福度が上がる
ウェルビーイング経営の目的は、従業員が幸せに暮らせるようにすることです。そのためウェルビーイング経営の取り組みが進めば、従業員の幸福度が上がります。
従業員の幸福度が上がることで仕事にも生き生きと取り組むようになり、企業全体の生産性が向上する可能性もあります。
人材確保をしやすくなる
ウェルビーイング経営に取り組むことで、企業イメージが向上し人材流出リスクが削減されます。厚生労働省の調査「令和元年版 労働経済の分析」でも、働き方の柔軟化や労働環境の見直しが離職率の低下、従業員の雇用定着率の上昇に繋がる可能性があると発表されています。
離職率の低さは、就職活動中の人材への有効的なアピールにもなります。長く働ける企業に勤めたいと考えている人材であれば、ウェルビーイング経営に取り組む企業に強い魅力を感じるでしょう。
チームワーク力が高まる
ウェルビーイング経営は、従業員のチームワーク力にも反映されます。HR総研が実施した調査では、ウェルビーイング経営に取り組む企業の従業員の中で「取り組みの推進により社内コミュニケーションの活性化の効果が出ている」と回答した割合は33%でした。
【「ウェルビーイング」の推進で得られている効果(上位5項目)】
|
社員エンゲージメント向上 |
57% |
|
社員モチベーション向上 |
50% |
|
社内コミュニケーションの活性化 |
33% |
|
会社全体の生産性向上 |
33% |
|
企業価値の向上 |
22% |
参考:HR総研 ウェルビーイングと健康経営に関するアンケート結果報告
従業員同士がコミュニケーションを取りやすい環境になれば関係性が良化され、社内のチームワーク力も向上するといえます。
ウェルビーイング経営を成功させるポイント

ウェルビーイング経営を導入する際に確認しておきたいポイントを3つ紹介します。
自社課題を徹底的に分析する
ウェルビーイング経営に取り組む際は、自社課題を導き出し、課題の解決に向けた取り組みを導入することが大切です。例えば在宅勤務者が多い企業では、運動不足の解消や従業員同士の交流機会の創出といった施策が効果的と考えられます。
まずはサーベイや面談を実施し、自社の従業員がどのような点に不満を感じているのか、現在の健康状態はどのようなレベルにあるのか調査してください。
労働環境を整備する
時間外労働や休日出勤の多い企業では、労働環境の整備が必要です。内閣府の調査「満足度・生活の質に関する調査報告2022」では、新型コロナウイルス感染症の影響により労働時間が減少したことで、従業員の生活満足度が向上したというデータが発表されました。
参考:内閣府政策統括官 満足度・生活の質に関する調査報告2022
残業規制や休暇制度を導入するなどして、従業員が十分に休息できる環境を整えてください。しっかりと休息しリフレッシュすることで、仕事に対するモチベーションも高まり集中力も回復します。心身共に余裕がある状態なら、自然とキャリアへの充実感や幸福度も向上します。
健康経営を推進する
健康経営とウェルビーイング経営は似て非なるものです。健康経営は従業員の健康維持または増進させるためのもので、ウェルビーイング経営は従業員が幸福感で満たされる生活を送ることが目的とされています。
しかし両者は「従業員の心身を健康にすること」という点で一致しており、完全に切り離して考えるものではありません。
健康経営においては健康経営優良法人認定という制度があり、評価が分かりやすいのが利点です。ウェルビーイング経営の一環として健康経営に取り組む際は、「健康投資管理会計ガイドライン」を参考にして自社の課題や現状を客観的に可視化してください。
個人で取り組めるウェルビーイング

ここからは、個人で取り組めるウェルビーイングの事例を紹介します。
法人のように戦略を練る、企画書を作成する、という大がかりなことをやる必要がないため、取り組みやすいことが特徴です。ぜひ気軽に取り入れてみてください。
周囲と積極的にコミュニケーションをとる
新型コロナウイルスの影響でテレワークが導入されるようになり、人と話す機会が減り、繋がりが薄れたように感じメンタルヘルスに不調をきたす人が増えました。
人間は社会的生き物ですから、必ず何かしらのコミュニティに所属しています。そのコミュニティ内の人たちと積極的に会話し、心を充実させましょう。
積極的に会話できる仲間がいない場合、SNSなどを利用して同じ趣味の仲間を見つけたり、友達を探すのもおすすめです。
もちろんSNSの利用にはリスクもありますが、自分と同じ悩みや不安を持つ人をフォローし、投稿をチェックするだけでも勇気づけられることは多いでしょう。
意識して身体を動かす
現代人はパソコンやスマートフォンを長時間見ることになりがちです。結果、眼精疲労や肩こりからくる不調に繋がる可能性があります。
少し身体を動かすように意識するだけでも、疲労度がぐっと変わります。
1時間に1回は電子機器から目を離して休憩する、トイレに行ったら肩を回してストレッチする、といったことから続けてみましょう。
ライフスタイルメディアから情報を取る
女性向けの事例になりますが、アラサー世代の女性へ向けたファッション誌・ライフスタイル誌である『CLASSY』では「ウェルビー女子」という単語が生まれています。
定義としては「心身ともにヘルシーな女性のこと」「忙しい毎日でも無理せず自分らしく暮らすアラサー女子のこと」と表現されています。
精神的にも経済的にも自立しており、休日には料理や運動といった余暇を楽しむ、そんな女性像が提案されているのです。
もちろんあくまで提案のため、この通りにふるまわなければならない、というわけではありません。
ただ、同世代の同性の取り組みを参考にして、共感できる箇所から毎日の生活に取り入れてみるのも良いでしょう。
今後、ウェルビーイングが注目されるにつれ、他の世代、他の性別をターゲットとしたメディアでもウェルビーイングに関する取り組みが特集されるようになるかもしれません。
ウェルビーイングに興味があるなら、そうした最新の情報には常にアンテナを張っておきましょう。
経営に関するウェルビーイングの事例

ここでは、経営に関連する法人のウェルビーイング関連事例を紹介します。
業界を問わず様々な取り組み事例があるので、自社の状況と照らし合わせながら導入の参考にしてみてください。
ユニリーバジャパン株式会社
ユニリーバジャパン株式会社は、歯ブラシやボディソープなどビューティー&パーソナルケア、ホームケア用品を製造する企業です。
ユニリーバジャパン株式会社では、2016年より「WAA」(ワー、Work from Anywhere and Anytime)と呼ばれる独自の人事施策を導入しました。従業員が柔軟に働けるよう、具体的には以下の取り組みを実施しています。
- 上司に申請すれば理由を問わず、会社以外の場所(自宅、カフェ、図書館など)でも勤務できる
- 平日の5時~22時の間で自由に勤務時間や休憩時間を設定できる
取り組みの結果、制度導入から10ヵ月後の従業員アンケートでは、従業員の75%が「生産性が上がった」、33%が「幸福度が上がった」と回答しました。また、「余計なストレスが軽減し、より仕事への意欲が増した」など生産性の向上を感じる声も出ています。
株式会社丸井グループ
出典:株式会社丸井グループ
株式会社丸井グループは、デパートの丸井やエポスカードなどをグループ企業に保有する企業です。社会全体を「しあわせ」あふれる場所にしていくことを目標に、ウェルビーイング経営を導入しています。株式会社丸井グループでの主な取り組み内容は、次の通りです。
- レジリエンスプログラム
- 健康経営推進プロジェクト
レジリエンスプログラムは経営陣向けのプログラムで、健康経営推進プロジェクトは従業員向けの施策です。
レジリエンスプログラムは、困難な状況下でもチャンスを見出し、主体的に行動できる人材・組織の育成を目指すための施策です。講座を受講する形で学びを深める内容になっており、「身体の健康」「情動の健康」「思考の健康」「精神性の健康」という4つの分野について学びます。
一方、健康経営推進プロジェクトは公募制となっており、積極的な活動が行われています。具体的な施策内容は次の通りです。
- ストレスチェックの実施
- 組織の活性度調査の実施
- 残業時間の削減
- 保健指導の導入
上記の取り組みの結果、「健康経営優良法人(ホワイト500)」に7年連続で選定、「スポーツエールカンパニー」にも選定されています。また、従業員の67%がウェルビーイング活動に参加するなど、健康意識の高まりも見られるようになりました。
参考:丸井グループ 人と社会のしあわせを共に創る「Well-being経営」
参考:ForbesJapan 医師と社長が掴んだゴール「リーダーのレジリエンスとは」
GoogleLCC
出典:GoogleLCC
GoogleLCCは、インターネット関連の製品やサービスを提供する企業です。GoogleLCCでは、「プロジェクト・アリストテレス」を導入し、世界的に大きな注目を集めています。
プロジェクト・アリストテレスは、「効果的なチームを可能とする条件は何か」という問いに対する答えを見つけ出すことを目的としたプロジェクトです。具体的にはピアボーナスという制度を導入しており、従業員同士で感謝の言葉を伝え合ったり、社内ポイントなどを送り合ったりしてきました。従業員のコミュニケーションの機会を増やすことで、チームワークが高まり従業員のモチベーションも向上します。
参考:GoogleLCC イノベーションが生まれる職場環境を作る
株式会社デンソー
株式会社デンソーでは、「仕事とプライベートの充実」「チームで働くこと」などを目標にウェルビーイング経営を導入しています。具体的な施策内容は次の通りです。
- ストレスチェックの実施
- こころの相談室の設置
- 個別面談の実施
- 睡眠状態のチェック
- 復職支援制度の整備
- メンタルヘルス研修の実施
活動の結果、個人の生活習慣を点数化したオリジナルの健康経営指標「生活習慣スコア」が改善しました。また、株式会社デンソーは6年連続で「健康経営優良法人 ホワイト500」にも選出されています。
PwCJapan
出典:PwCJapan
PwCJapanは、世界4大会計事務所のうちのひとつです。「成功する人々はウェルビーイング(心身の幸福)を軽視しない。成功する組織はそこで働く人々がウェルビーイングを追求できるような環境を提供する。」という考えのもと、ウェルビーイング経営を推進しています。具体的な施策は次の通りです。
- 予防接種の補助
- 健康電話相談システム
- ウェルビーイングセミナーの実施
- ストレスチェック
- メンタルヘルス研修
- 職場復帰支援プログラムの導入
取り組みの結果「日常的に運動をしている」職員の割合は44.6%となり、前回の37.2%から向上しました。さらに「食事に気を遣っている」「十分な睡眠が取れている」と回答した従業員は70%を超え、ウェルビーイング経営の考え方が従業員に浸透しつつあります。
トヨタ自動車株式会社

出典:トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社は、国内のみならず国外にも多くの支社を持つグローバル企業です。
世界中の人が幸せになるモノやサービスを提供するため、従業員が心身ともに健康で活躍し続けることを企業活動の基盤としています。
経営理念であるトヨタフィロソフィーの中には「わたしたちは、幸せを量産する。」と明記されており、従業員のウェルビーイングについて積極的に取り組んでいることがわかるでしょう。
トヨタ自動車株式会社には生産性に重きを置いている企業、といったイメージがありますが、ここでのポイントは企業だけでなく従業員の幸せのための生産性という点です。
具体的な取り組みとしては以下があります。
- ストレスチェックの実施
- 機関紙や社内メールを通した、ヘルスリテラシー向上の情報発信
- 育児・介護休業からの復職率上昇
- 年次有給休暇の取得率上昇
- 時間外労働の減少
- 休憩時間や隙間時間の肩こり解消チャレンジの実施
また、VALUEであるトヨタウェイにも「パートナー」という欄があり「ともに幸せをつくる仲間(顧客、社会、コミュニティ、従業員、ステークホルダー)を尊重し、それぞれの力を結集する。」と記載されています。
このことから、単に従業員の枠に留まらず、より大きな社会まで見据えた枠組みの中で、それぞれが幸せを追求するウェルビーイングに取り組んでいることが分かります。
参考:トヨタ自動車健康保険組合
楽天グループ株式会社

出典:楽天グループ株式会社
楽天グループ株式会社は、Eコマースや通信など様々なサービスを展開している企業です。
楽天グループ株式会社は、企業も個人も、自らの進むべき方向性を自律的に選択することが求められる時代になっていくことを見越し、ウェルビーイングに取り組んでいます。
具体的には、楽天ピープル&カルチャー研究所にて「コレクティブ・ウェルビーイング」という、ウェルビーイングに関するガイドラインを作成しています。
楽天グループ株式会では、コレクティブ・ウェルビーイングを「ある目的のもとに、ありたい姿を持つ多様な個人がつながりあった持続可能なチームの状態」と定義しています。
そのために、「企業」と「働く個人」の両側面から「仲間」「時間」「空間」の3つの要素の設計と、それぞれに「余白」を設けることを大切にしています。
特にこの「余白」は特徴的な考え方であり、心にゆとりを持つからこそ、仕事にも精力的に取り組めるという姿勢が現れているといえるでしょう。
では、その「仲間」「時間」「空間」と「余白」を実施するための施策として何があるかというと、具体的には以下です。
- チームメンバーが大切にしている価値観を理解する
- オン/オフの切り替えやリフレッシュの予定を計画する
- 能力を最大限発揮するために、仕事場の環境やツールを整備する
このようにして持続的なチームの在り方を検討しています。会社が組織である以上、人の出入りは避けては通れません。
それでも、同じ目的を共有して繋がり合えば、持続的なチームを作ることができるのではないか、ということを教えてくれる事例です。
味の素株式会社

出典:味の素株式会社
食品の製造・販売を行う味の素株式会社は、従業員の健康を経営における重要項目として捉え、戦略として取り組んでいます。
味の素株式会社では、食品メーカーらしく、食事、運動、睡眠を中心とした生活習慣を重視した健康推進に積極的です。
例えば、「My Health」という従業員専用ウェブサイトでは、自身の健康診断や生活習慣といった健康データを蓄積できる機能があり、従業員が自発的に健康管理に取り組むセルフ・ケアを推奨しています。
さらに、従業員のみならず、その家族の健康の重要性まで戦略の中に明記している点も特徴です。
味の素株式会社の取り組みの中心はセルフ・ケアにあり、健康情報を自発的に入手し、人に説明できるくらい理解する状態が求められています。
その結果、従業員ひとりひとりの健康意識が上がり、心身ともにいきいきと働けるオフィス環境に繋がっているといえるでしょう。
参考:味の素株式会社 健康経営
株式会社アシックス

出典:アシックス株式会社
株式会社アシックスは、スポーツや健康関連の商品やサービスを提供している企業であり、個人と企業が一緒に成長できる企業文化の醸成に取り組んでいます。
株式会社アシックスでは健康経営の一環として「ASICS健康経営宣言」も制定しました。
ASICS健康経営宣言とは、「従業員とその家族の”Well-being(身体的・精神的・社会的に良好である状態)”を目指し、健康推進活動を行っていく」という宣言で、健康経営とウェルビーイングが密接に関わっていることを示しています。
また、株式会社アシックスは自社の強みを活かし、自社開発の健康増進プログラム「ASICS HEALTH CARE CHECK」を従業員に実施してきました。
具体的な取り組みとしては、次のようなものがあります。
- ストレスチェック
- 保健師による全従業員面談
- 運動推進セミナー
- アシックスアトリウム
- メンタルヘルス研修
- 治療と仕事の両立支援
これらの施策を通して、メンタル面とフィジカル面の双方から健康増進にアプローチしています。
特に、持病を抱えていても、仕事と両立できる環境整備に取り組んでいるのは、健康に関するサービスを提供している自社の強みを活かした考え方です。
ツカサ工業株式会社

出典:ツカサ工業株式会社
ツカサ工業株式会社は、粉を扱うさまざまな機械やプラントを設計・製造・販売しているメーカーであり、「健康経営優良法人2021」にも認定されています。
ツカサ工業株式会社の健康経営・ウェルビーイングに関する取り組み事例は、次のとおりです。
- 残業時間管理による時間外労働の削減
- バースデー休暇導入等有給取得率の向上
- 各種ハラスメントや嫌がらせを排除し従業員の人権を尊重
- 健康診断やメンタルヘルスチェックを年一回実施、インフルエンザ予防接種社内接種(費用会社負担)
- 「座りすぎ」による健康リスクを軽減するため、昇降式デスクを全事務所に導入
- 屋内禁煙(敷地内での喫煙は指定の中庭のみ可)
そのほかにも、広く日本の未来の視点から、次世代を担う子ども達の育成にも貢献しています。
具体的には「半田市少年少女発明クラブ」を設立し、子どもたちに「作る楽しさ」や「工夫する楽しさ」を伝え、創造力豊かな人間を育成する教室を開いています。
また、地元教育機関からの職場体験の受け入れも実施しており、未来の日本の「モノづくり」を支える子ども達を育て、支援しています。
自社ならではの取り組みを作るポイント

他社の取り組みをそのまま真似しても、自社とは状況が異なるため上手くいくかどうか分かりません。自社ならではの取り組みを実現するため、次のポイントを見ていきましょう。
自社の特徴を踏まえる
ウェルビーイングに取り組む際は、自社の特徴を踏まえて実施内容を考えるのがおすすめです。
例えばパソコン仕事が多い職場環境であれば、日頃できない自然の中で身体を動かす機会をつくる、高いサービス精神が重視される業態なら、従業員もお客様としてもてなし、日頃の感謝を込める。
上記のように、自社の特徴を分析することで、自社のスタイルを強化することができます。
従業員アンケートを取る
経営陣で考えても案が出てこない、これでいいのか分からない、従業員の考えていることが読めない、といった悩みがある場合、直接聞くのもよいでしょう。
従業員が何を望んでいるのかアンケートを取るなどして、現場の生の意見を吸い上げてみましょう。
このアンケート作成も、まったくのゼロベースの記述式にするのか、ある程度の選択肢を持たせた形式にするのか、やり方は様々です。
正解はありませんが、あくまで「自社をよりよくするにはどうすれば良いか」の視点から取り組めるとよいでしょう。
業界や規模間が似た企業をリサーチする
自社と業界や規模間が似た企業が、どのようにウェルビーイングに取り組んでいるのかを調べます。
もちろんゼロから考えることも大切ですが、他社の良い部分は積極的に真似することで、より最短でウェルビーイングに取り組むことができます。
何をしているのか具体的な事例を知ることで、サンプルの幅が広がります。それによって真似をしやすい箇所が分かったり、自社ならではの独自性に気づくことができるでしょう。
対面でコミュニケーションをとる
ただ単に、ウェルビーイングが大事だといわれているから、そのまま機械的に実践しました、という取り組み方だと、たとえ理論上は合っていても、従業員の心はついてきません。
地道な日々の対面コミュニケーションをとってこそ、経営陣側の意見も伝わりますし、従業員側の意見も知ることができます。
お互い歩み寄ることで社内の風通しがよくなり、自社にとって本当に必要なウェルビーイングの取り組みにつながるでしょう。
まとめ:ウェルビーイングの事例を知って経営に活かそう

ウェルビーイングは、心身ともに健康に生きていくために大切な考え方です。ますます多様化していく時代において、その考え方の重要性はさらに上がっていくでしょう。
従業員と企業のどちらか片方ではなく、両方が主体的にウェルビーイングに取り組むことで、より効果も上がりやすくなります。
今回ご紹介した事例を参考にしながら、積極的に行動してみましょう。
また、従業員の健康増進を目標としているなら、ぜひKIWI GOアプリを使ってみてください。
従業員の運動と社内交流を推進するために開発されたアプリであるため、従業員の運動不足やコミュニケーション不足にお悩みの企業におすすめです。