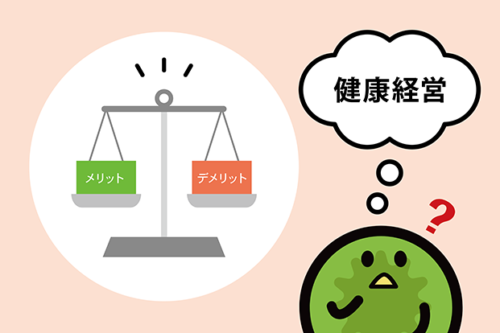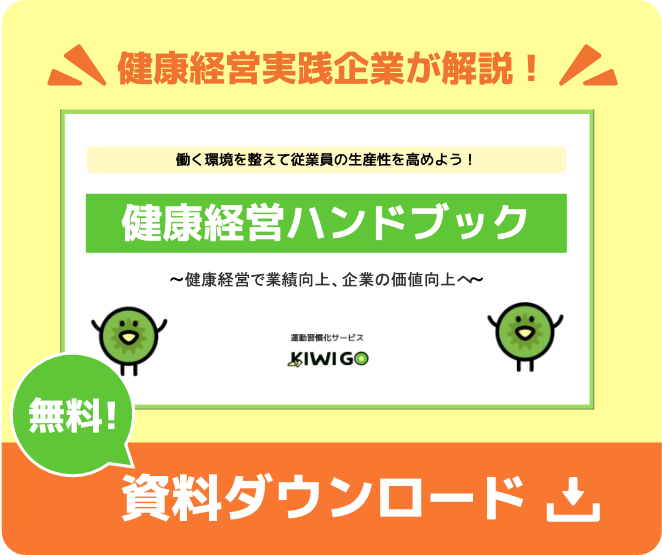ウェルビーイングとは肉体的、精神的、そして社会的に全てが満たされた状態を指します。
従業員がより幸福に健康で働けるよう、企業経営にウェルビーイングを取り入れることは重要です。
しかし施策をどう進めるべきか、悩む企業は少なくないでしょう。
そこでこの記事では、ウェルビーイングの意味や概要、ウェルビーイングを向上させるためのポイントなどを紹介します。
具体的な対策やメリットも解説するため、ウェルビーイング施策の導入を検討中の方は必見です。ぜひ、参考にしてみてください。
目次
ウェルビーイングとは

ウェルビーイングとは、1964年にWHO(世界保健機関)が発表した「世界保健機関憲章」に記載されている言葉です。
「健康」「幸福」「福祉」と訳されており、「社会的にも精神的にも肉体的にも満たされた状態であること」を意味します。
ウェルビーイングが注目を集めたきっかけは、2021年に開催された世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)です。この会議で「グレートリセット」を通じてモノの豊かさが尊重されたこれまでの価値観が変わり、新しい価値観を創造していくフェーズに突入しました。
あわせて読みたい:ウェルビーイングとは?経営における重要キーワードの意味と対策を解説
ウェルビーイングにおける日本の現状

日本におけるウェルビーイング実感度は低く、世界の国々と比較して後れを取っているのが現状です。
ここでは、具体的な調査結果を用いて日本の現状について解説します。
日本のウェルビーイング実感度は25%
Global Wellbeing Initiativeと日本版Well-being Initiativeが共同で実施している調査において、2021年度の日本におけるウェルビーイング実感度は25%でした。
直近5年間の調査結果は以下の通りです。
|
年度 |
ウェルビーイングの実感度 |
|
2017年 |
23% |
|
2018年 |
22% |
|
2019年 |
26% |
|
2020年 |
27% |
|
2021年 |
25% |
2006年や2007年は30%を超えていたものの、2008年のリーマンショック以降は20%台にとどまっています。
また新型コロナウイルス感染症の影響からか、2021年以降再びウェルビーイングの実感度は減少しています。
参考:ウェルビーイング学会 日本のウェルビーイング実感の経年変化
日本のウェルビーイング満足度は44%
株式会社バークレーバウチャーズの調査において、調査を実施した世界15ヵ国の中で、日本のウェルビーイング満足度は世界最下位となりました。
|
国(一部抜粋) |
ウェルビーイング満足度 |
|
インド |
88% |
|
メキシコ |
81% |
|
アメリカ |
77% |
|
ドイツ |
74% |
|
イギリス |
71% |
|
フランス |
67% |
|
イタリア |
63% |
|
日本 |
44% |
当該調査における日本のウェルビーイング満足度は44%ですが、世界において満足度が低い国でも50%は超えているケースが多くあります。そのためこの調査では、日本のウェルビーイング満足度の低さが顕著になっているといえます。
参考:株式会社バークレーヴァウチャーズ 2016年度Edenred-Ipsos Barometer調査
ウェルビーイングを導入する日本の企業は約半数
総務専門誌『月刊総務』を発行する株式会社月刊総務の調査では、日本では約半数の企業がウェルビーイング向上に対する取り組みを導入していると回答しています。
日本においては、特にフィジカルウェルビーイング(※1)に注力している企業が多いのが特徴です。
一方、ソーシャルウェルビーイング(※2)やコミュニティウェルビーイング(※3)は点数が低いことも明らかになっています。
質問:「あなたの会社ではウェルビーイングに取り組んでいますか」
|
回答 |
割合 |
|
とても取り組んでいる |
10.0% |
|
やや取り組んでいる |
41.8% |
|
全く取り組んでいない |
48.2% |
【具体的な取り組み内容】
|
フィジカルウェルビーイング |
68.4% |
|
キャリアウェルビーイング |
63.2% |
|
ソーシャルウェルビーイング |
43.9% |
|
コミュニティウェルビーイング |
38.6% |
|
ファイナンシャルウェルビーイング |
22.8% |
※1:「フィジカルウェルビーイング」:身体的に幸福であること、心身が健康であること
※2:「ソーシャルウェルビーイング」:人間関係において幸福を感じる関係性を築けていること
※3:「コミュニティウェルビーイング」:「社会的なウェルビーイング」「社会的な幸福」であること
この調査結果を見ると、日本において約半分の企業はウェルビーイングに取り組めていないと分かります。日本におけるウェルビーイング向上に対する取り組みは、世界的に見て不十分であるといえます。
ウェルビーイングを向上させる要素・行動

ここからはより実践的にウェルビーイング向上を目指すため、ウェルビーイングを構成する要素を解説します。
【海外】ウェルビーイングの指標となる要素
ウェルビーイングの指標とされているモデルケースは主に「PERMAモデル」と「ギャラップ社のモデル」の2種類です。
それぞれの構成要素は以下の通りです。
【PERMAモデル】
|
Positive emotion |
ポジティブで明るい感情を抱くこと |
|
Engagement |
物事に積極的に取り組むこと |
|
Relationship |
他者と良好な人間関係を築くこと |
|
Meaning |
人生の意義を自覚すること |
|
Accomplishment |
動を通して達成感を味わうこと |
【ギャラップ社のモデル】
|
Social Wellbeing |
良好な人間関係における幸福度 |
|
Community Wellbeing |
地域社会とのつながりにおける幸福度 |
|
Physical Wellbeing |
体や精神が元気な状態で得られる幸福度 |
|
Financial Wellbeing |
満足できる生活を送る際に必要な経済的な幸福度 |
|
Career Wellbeing |
仕事や趣味を含めた、自分が時間を費やしている生活の主たる活動における幸福度 |
ウェルビーイング満足度を向上させるには、上記の要素をクリアできるよう働きかけを強める必要があります。
参考:ギャラップ社 The Five Essential Elements of Well-Being
参考:PERMA257JAPAN ポジティブ心理学とPERMA
【日本】ウェルビーイングの指標となる要素
慶應義塾大学大学院の前野隆司教授は、幸福を感じる4つの因子を次のとおり提唱しています。
|
やってみよう因子 |
夢や目標ややりがいを持ち、「なりたい自分」を目指して成長していくこと |
|
ありがとう因子 |
多様な人と繋がりを持ち、他者に親切にしたり感謝したりすること |
|
なんとかなる因子 |
前向きで、自己受容ができており、楽観的であること |
|
ありのままに因子 |
人目を気にせず、自分らしく生きていくこと |
指標を利用すれば、ウェルビーイングの向上に向けてやるべきことが明確になります。
なお、ウェルビーイングの導入時に使用する指標に厳密な決まりはありません。自社の課題や目標に合うものを選択してください。
参考:Sustainable Smart City Partner Program アドバイザー活動紹介
ウェルビーイングを向上させるメリット

ここでは従業員のウェルビーイングが向上により、企業や従業員が得られるメリットを3つ紹介します。
モチベーションや生産性が向上する
従業員がやる気を持って生き生きと仕事をすることでパフォーマンス力が向上し、企業全体の生産性向上にもつながります。
厚生労働省の発表した「令和元年版 労働経済の分析」の調査結果は以下の通りです。
【働きがいと個人の労働生産性に関する認識 】
|
働きがいのスコア |
生産性向上の実感度 |
|
2以下 |
2.37 |
|
3 |
2.93 |
|
4 |
3.36 |
|
5 |
3.84 |
|
6 |
4.39 |
上記の結果から、ワーク・エンゲイジメントが高いほど、労働生産性が高まっていると感じやすいことがわかります。
離職率の低下につながる
厚生労働省は「令和元年版 労働経済の分析」にて、働き方の柔軟化や労働環境の見直しが離職率の低下、従業員の雇用定着率の上昇に繋がる可能性があると発表しました。
そのためウェルビーイング向上施策の導入は、特に人材確保が難しい企業にとって必要であるといえます。
優秀な人材が企業に残る、あるいは、別の人材が企業に集まるようになれば、企業価値や企業イメージもさらに向上します。
従業員のコミュニケーションが円滑になる
HR総研が実施した調査において、ウェルビーイング推進により「社内コミュニケーションの活性化」の効果が出ていると回答した方は33%でした。
【「ウェルビーイング」の推進で得られている効果(上位5項目)】
|
社員エンゲージメント向上 |
57% |
|
社員モチベーション向上 |
50% |
|
社内コミュニケーションの活性化 |
33% |
|
会社全体の生産性向上 |
33% |
|
企業価値の向上 |
22% |
従業員同士のコミュニケーションが活性化すれば、仕事の相談がしやすくなり業務が円滑に進みます。
また副次的にチームワークやパフォーマンス力も向上します。
参考:HR総研 ウェルビーイングと健康経営に関するアンケート結果報告
企業がウェルビーイングを向上させる方法

HR総研の「ウェルビーイングと健康経営に関するアンケート結果報告」では、ウェルビーイング実現に向けて実施している取り組みについて、次の調査結果が出ています。
【「ウェルビーイング」の実現に向けた取組み施策※実施予定含む(上位5項目)】
|
多様な働き方の推進 |
50% |
|
健康経営の推進 |
49% |
|
コミュニケーションの活性化 |
47% |
|
長時間労働の是非 |
47% |
|
社員のキャリア自律の支援 |
36% |
ここでは上記のアンケート結果を基に、企業がウェルビーイングを向上させるために導入したい具体的な施策を4つ紹介します。
参考:HR総研 ウェルビーイングと健康経営に関するアンケート結果報告
労働環境を見直しする
独立行政法人経済産業研究所が発表した論文では、「1日の労働時間が10時間半を超えたところから急激に生活満足度が低下することが見出されている」と発表されています。
特に女性は6~7 時間程度で生活満足度が平均以下となり、その後勤務時間が増加するにつれて徐々に生活満足度が低下していくと明らかになりました。
参考:独立行政法人経済産業研究所 労働時間が生活満足度に及ぼす影響
また内閣府の「満足度・生活の質に関する調査報告2022」では、新型コロナウイルス感染症の影響により労働時間が減少し、生活満足度が向上したというデータも出ています。
参考:内閣府政策統括官 満足度・生活の質に関する調査報告2022
長時間労働や時間外労働があると、従業員の精神的な満足度が低下する恐れがあります。定時退社の日を設けたり有休休暇の取得を促したりしながら、労働環境の正常化に努めてください。
福利厚生を整備する
ウェルビーイングの推進に際して、福利厚生を整えるのも方法のひとつです。福利厚生の具体例は次のとおりです。
- 食事や昼食の補助
- 住宅手当や家賃補助
- 運動インセンティブの付与
- 社内託児所の設置
- リフレッシュ休暇の導入
- 教育費用の補助
- 宿泊施設やレジャー施設の割引制度の導入
株式会社学情が就活中の学生に行ったアンケートでは、ウェルビーイング充実のために重視している点に「休日休暇・勤務時間に関する制度」を挙げた人が最多となりました。
【自身の「ウェルビーイング」を追求するために重視している点(上位5項目)】
|
休日休暇・勤務時間に関する制度 |
61.0% |
|
企業の雰囲気社風と相性 |
55.0% |
|
福利厚生 |
54.8% |
|
仕事内容 |
50.8% |
|
働きがい |
42.2% |
福利厚生が充実していると、従業員のウェルビーイング向上に役立ちます。また企業イメージが向上することで、優秀な求職者の獲得にもつながります。
健康経営を推進する
健康経営とは、従業員の健康を守るために企業が実施する施策です。健康経営には健康経営優良法人認定制度が導入されており、評価が分かりやすいのが特徴です。
また健康投資管理会計ガイドラインを活用すれば、自社の状況を可視化できます。
あわせて読みたい:健康投資管理会計とは?ガイドラインを使った実施の流れも解説!
ウェルビーイングと健康経営の厳密な意味合いは異なりますが、健康経営を推進することは後のウェルビーイングにつながります。健康経営の方法、施策については以下の記事もぜひ参考にしてみてください。
あわせて読みたい:ウェルビーイングと健康経営の違いとは?注目の理由や事例を紹介
社内コミュニケーションを活性化する
ハーバード大学のロバート・ウォールディンガー博士は、「ハーバード成人発達研究」にて1938年から約80年、724名の男性を調査し続けた結果「私たちの健康と幸福には、良い人間関係が必要だ」と結論付けています。
参考:LIFE SPAN RESEARCH Helping You Create a Happier Life
参考:ニューズウィーク日本版 ハーバード大学が80年間724人を追跡調査して解明した「
職場の人間関係を良好にすることで、お互いに悩みを相談しやすい環境が生まれます。
また周りの人が自身の意見を受け入れてくれる環境が構築されることで、気兼ねなく働ける環境が整います。
また、「休んだ分頑張って働こう」「自分も〇〇さんのようになりたい」と相乗効果が生まれる可能性も少なくありません。
効果的にウェルビーイングを向上させる取り組みのポイント

従業員のウェルビーイングを向上させるためには、リモートワークの推進やコアタイムの導入などを実施し、働き方を多様化させることが大切です。
また社内コミュニケーション向上に向けて、従業員同士の交流できる機会を設けたり社内運動会を開催するといった取り組みも必要です。
定期的にサーベイを実施し、従業員の悩みや本音を聞きましょう。現場のニーズに対応した施策を柔軟に取り入れ、定期的に見直してください。
まとめ:ウェルビーイング向上にはコミュニケーションの活性化が必要

日本におけるウェルビーイングの現状は望ましいものではなく、改善の余地があります。
ウェルビーイングを向上させるためには、「福利厚生の整備」や「労働環境の見直し」「コミュニケーションの活性化」などといった取り組みが必要です。自社の課題や従業員のニーズに合った施策を導入してください。
ウェルビーイング向上のため具体的に何をすればよいのかお悩みの方は、「KIWI GO」がおすすめです。
「KIWI GO」は従業員の健康促進や、コミュニケーションの活性化を目的とする運動習慣化アプリです。同じ企業の方々と交流を楽しんだり一緒に運動したりすることで、コミュニケーションの機会が増えます。
またウォーキングの習慣がつくことで身体的、精神的な健康にも繋がります。
「従業員同士の交流の機会を増やしたい」「労働環境をよくしたい」と考えている企業は、ぜひKIWI GOをご活用ください。